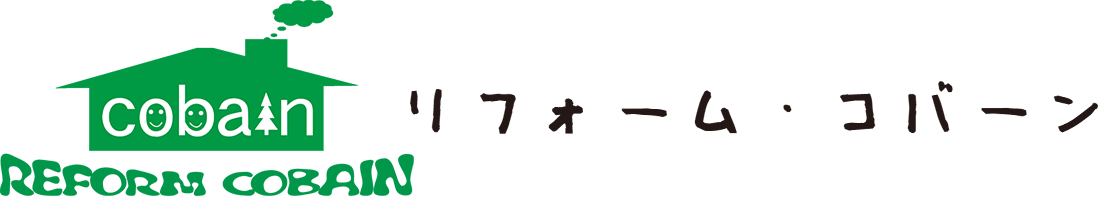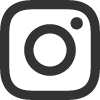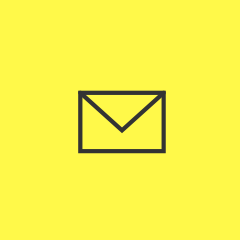祈り。。。
みなさん こんにちは
今回のブログは、少し長いですが
今なお 決死の任務に取り掛かられておられる方々の
ニュースを読み、ブログで紹介せずにはいられませんでした。
産経新聞 3月31日(木)7時56分配信
ズドン。重い爆発音が響き渡った。今月14日午前11時1分、東日本大震災で被災した東京電力福島第1原発3号機が水素爆発を起こし、原子炉建屋の上部が吹き飛んだ。東電の下請け業務を行う協力会社のベテラン社員、根本誠さん(47)=仮名=は、隣の2号機で電源復旧作業に当たっていた。
外へ出ると3号機は鉄の骨組みがむき出しになり、コンクリートのがれきが散乱していた。灰色の煙がもうもうと青空へ立ち上っていた。
「もうだめだ…」
仲間の声が聞こえた。根本さんは「放射線をくらうぞ。避難するんだ」と声を上げて防護服のまま、がれきの上を走った。乗ってきた車3台は爆風で窓が割れていて使えず、作業基地となっている免震重要棟まで1キロ近く、最後は息切れして歩いてたどり着いた。
全員の無事を確認し、同僚4人ほどと喫煙室で「やばかった」「もし外にいたらかなりの線量をくらっていた」と話した。仲間を見ると、たばこを持つ手が震えていた。
根本さんは11日の震災発生時、第1原発の事務所3階にいた。東電の要請に応え、同僚十数人とそのまま原発に残った。
「被曝(ひばく)の危険性があることは分かっていたが、復旧作業には原発で18年働いてきた俺たちのような者が役に立つ。そう覚悟を決めた」
4日間働き続け、水素爆発に遭遇した翌日に当たる15日朝、東電の緊急退避命令により避難した。
東電によると、第1原発では連日300~500人が働き、30日は東電社員253人、協力会社の社員50人の計303人に上った。1日の食事は非常食2食、毛布1枚にくるまり雑魚寝という過酷な環境で作業を続ける彼らの大半は、地元の住民である。
現在は避難生活を送る根本さんは「会社は『すぐ来てくれ』など命令的なことは決して口にしない。ただ『覚悟が決まったら来てほしい』と言う。自己責任を求められる」と話す。
3号機の発電用タービン建屋地下で24日、放射性物質(放射能)に汚染された水で被曝した作業員3人も根本さんの部下らだった。東電社員の中には5日間で年間被曝線量の上限の50年分を浴びた人もいた。
被曝という生命の危険を冒してまで、なぜ彼らは行くのか。
◇
■原発復旧、それぞれの使命感
■「誰かがやらねば」「国民のため」「最後まで戦う」
■消防隊員「絶対お役に立って帰る」
東京電力福島第1原発で保守の仕事を請け負う会社に勤める佐藤大輔さん(27)=仮名=は今月16日、同僚20人とマイクロバスに乗り第1原発へ向かった。元請けの協力会社から打診され「行きます」と志願した。5号機の冷温保持にかかわる作業だった。
「原子炉が爆発したら終わりだが、この仕事を9年間続けてきた経験から、招集がかかるうちは何とかなると判断した。ただ、中には会社員として行かざるを得ないという人もいて、車内の空気は沈んでいた。年長の作業員は『もう死ぬのか』と青い顔をしていた」
佐藤さんは、15日に2号機が爆発した際、現場から5キロ地点のオフサイトセンター(緊急事態応急対策拠点)にいた経済産業省原子力安全・保安院の職員らが約50キロ離れた郡山市まで退避したことを挙げ、こう話した。
「誰かがやらなきゃならないことだから、やっている。ほかの専門的な仕事と職種が違うだけのことだと思う。保安院の人たちもそこに作業員がいる限り、とどまるのが仕事ではないか。専門家が住民より遠くへ逃げたら、誰を信じればいいのか。そういう人たちがいるから、原発へ行く者が英雄視されるのではないか」
◆レスキュー隊・自衛隊
復旧作業には、地元住民ら作業員だけでなく東京消防庁のハイパーレスキュー隊や自衛隊、警視庁などの「応援組」も放水活動のために駆けつけた。
大阪市消防局は53人が20日夜から90時間、東京消防庁の活動を支援した。本人の意思を確認した上で、職務命令が出される事実上の志願だった。指揮を執った片山雅義警防担当課長代理(48)は「東京消防庁が孤軍奮闘、国民のために命がけで戦っているのを、同じ消防職員として見過ごすわけにはいかない思いだった」と語った。
「私の息子は24歳だが、ほぼ同じ年齢の東京の隊員が体を震わせながら、『任務ですから』とだけ言い残して出動していった」
原発から約20キロ地点の前進基地から、800メートル地点の指揮所までサイレンを鳴らし移動中、自分たちに向かってお年寄りら6人ほどの住民がおじぎをした。
片山さんは「腰を90度まで曲げて、深々とおじぎをされた。その姿を見て、これは絶対に何かお役に立って帰らなければと思った」と話した。
◆東電社員・警察官
かつて有数の出稼ぎ地帯だった福島県の太平洋岸「浜通り」地方。
この地に昭和42年の福島第1原発1号機の着工から平成5年の広野火力発電所4号機の完成まで、四半世紀にわたり原発10基、火力4基が作られた。福島大学の清水修二副学長(62)=財政学=の研究によれば、総事業費は2兆円余り、月当たり71億円に上った。
清水さんは「建設が終わった後も運転保守の仕事が続き、6町2村で人口約7万2千人の双葉郡の2世帯に1人は発電所で働いている。現在、復旧作業を続けているのは使命感や責任感もあるだろうし、原発への依存度が高いがゆえに『生活のため』という面もあるだろう。地元にはそういう現実がある」と指摘する。
第2原発で第1原発の復旧を支援する東電の女性社員は本社の上司へ次のような電子メールを送った。
《実家の両親も津波に流され、いまだに行方がわかりません。すぐにでも飛んでいきたい…。被災者である前に、東電社員としてみんな職務を全うしようと頑張っています。私たちは最後まで戦います》
発生当初から復旧作業に当たり、現在は避難生活を送る根本誠さんは、来週にも第1原発へ戻るという。
「消防や自衛隊の方は公務だから、われわれ会社員とは使命感の持ちようも異なるかもしれない。同僚たちは今も原発で働いている。少ない人数で頑張っている。むろん、行かなくても誰も責めないだろうが、自分がよしとはできない。仲間のために自分は行く」
外へ出ると3号機は鉄の骨組みがむき出しになり、コンクリートのがれきが散乱していた。灰色の煙がもうもうと青空へ立ち上っていた。
「もうだめだ…」
仲間の声が聞こえた。根本さんは「放射線をくらうぞ。避難するんだ」と声を上げて防護服のまま、がれきの上を走った。乗ってきた車3台は爆風で窓が割れていて使えず、作業基地となっている免震重要棟まで1キロ近く、最後は息切れして歩いてたどり着いた。
全員の無事を確認し、同僚4人ほどと喫煙室で「やばかった」「もし外にいたらかなりの線量をくらっていた」と話した。仲間を見ると、たばこを持つ手が震えていた。
根本さんは11日の震災発生時、第1原発の事務所3階にいた。東電の要請に応え、同僚十数人とそのまま原発に残った。
「被曝(ひばく)の危険性があることは分かっていたが、復旧作業には原発で18年働いてきた俺たちのような者が役に立つ。そう覚悟を決めた」
4日間働き続け、水素爆発に遭遇した翌日に当たる15日朝、東電の緊急退避命令により避難した。
東電によると、第1原発では連日300~500人が働き、30日は東電社員253人、協力会社の社員50人の計303人に上った。1日の食事は非常食2食、毛布1枚にくるまり雑魚寝という過酷な環境で作業を続ける彼らの大半は、地元の住民である。
現在は避難生活を送る根本さんは「会社は『すぐ来てくれ』など命令的なことは決して口にしない。ただ『覚悟が決まったら来てほしい』と言う。自己責任を求められる」と話す。
3号機の発電用タービン建屋地下で24日、放射性物質(放射能)に汚染された水で被曝した作業員3人も根本さんの部下らだった。東電社員の中には5日間で年間被曝線量の上限の50年分を浴びた人もいた。
被曝という生命の危険を冒してまで、なぜ彼らは行くのか。
◇
■原発復旧、それぞれの使命感
■「誰かがやらねば」「国民のため」「最後まで戦う」
■消防隊員「絶対お役に立って帰る」
東京電力福島第1原発で保守の仕事を請け負う会社に勤める佐藤大輔さん(27)=仮名=は今月16日、同僚20人とマイクロバスに乗り第1原発へ向かった。元請けの協力会社から打診され「行きます」と志願した。5号機の冷温保持にかかわる作業だった。
「原子炉が爆発したら終わりだが、この仕事を9年間続けてきた経験から、招集がかかるうちは何とかなると判断した。ただ、中には会社員として行かざるを得ないという人もいて、車内の空気は沈んでいた。年長の作業員は『もう死ぬのか』と青い顔をしていた」
佐藤さんは、15日に2号機が爆発した際、現場から5キロ地点のオフサイトセンター(緊急事態応急対策拠点)にいた経済産業省原子力安全・保安院の職員らが約50キロ離れた郡山市まで退避したことを挙げ、こう話した。
「誰かがやらなきゃならないことだから、やっている。ほかの専門的な仕事と職種が違うだけのことだと思う。保安院の人たちもそこに作業員がいる限り、とどまるのが仕事ではないか。専門家が住民より遠くへ逃げたら、誰を信じればいいのか。そういう人たちがいるから、原発へ行く者が英雄視されるのではないか」
◆レスキュー隊・自衛隊
復旧作業には、地元住民ら作業員だけでなく東京消防庁のハイパーレスキュー隊や自衛隊、警視庁などの「応援組」も放水活動のために駆けつけた。
大阪市消防局は53人が20日夜から90時間、東京消防庁の活動を支援した。本人の意思を確認した上で、職務命令が出される事実上の志願だった。指揮を執った片山雅義警防担当課長代理(48)は「東京消防庁が孤軍奮闘、国民のために命がけで戦っているのを、同じ消防職員として見過ごすわけにはいかない思いだった」と語った。
「私の息子は24歳だが、ほぼ同じ年齢の東京の隊員が体を震わせながら、『任務ですから』とだけ言い残して出動していった」
原発から約20キロ地点の前進基地から、800メートル地点の指揮所までサイレンを鳴らし移動中、自分たちに向かってお年寄りら6人ほどの住民がおじぎをした。
片山さんは「腰を90度まで曲げて、深々とおじぎをされた。その姿を見て、これは絶対に何かお役に立って帰らなければと思った」と話した。
◆東電社員・警察官
かつて有数の出稼ぎ地帯だった福島県の太平洋岸「浜通り」地方。
この地に昭和42年の福島第1原発1号機の着工から平成5年の広野火力発電所4号機の完成まで、四半世紀にわたり原発10基、火力4基が作られた。福島大学の清水修二副学長(62)=財政学=の研究によれば、総事業費は2兆円余り、月当たり71億円に上った。
清水さんは「建設が終わった後も運転保守の仕事が続き、6町2村で人口約7万2千人の双葉郡の2世帯に1人は発電所で働いている。現在、復旧作業を続けているのは使命感や責任感もあるだろうし、原発への依存度が高いがゆえに『生活のため』という面もあるだろう。地元にはそういう現実がある」と指摘する。
第2原発で第1原発の復旧を支援する東電の女性社員は本社の上司へ次のような電子メールを送った。
《実家の両親も津波に流され、いまだに行方がわかりません。すぐにでも飛んでいきたい…。被災者である前に、東電社員としてみんな職務を全うしようと頑張っています。私たちは最後まで戦います》
発生当初から復旧作業に当たり、現在は避難生活を送る根本誠さんは、来週にも第1原発へ戻るという。
「消防や自衛隊の方は公務だから、われわれ会社員とは使命感の持ちようも異なるかもしれない。同僚たちは今も原発で働いている。少ない人数で頑張っている。むろん、行かなくても誰も責めないだろうが、自分がよしとはできない。仲間のために自分は行く」
本当に頭が下がる思いです。
私には、祈ることしかできません。
一刻も早く 皆様に平穏が訪れますように。